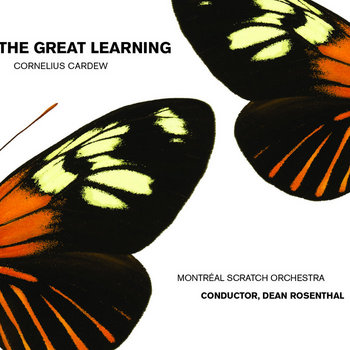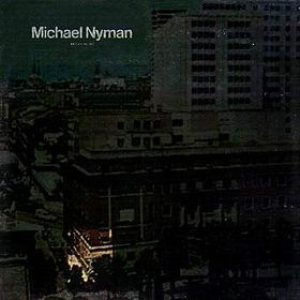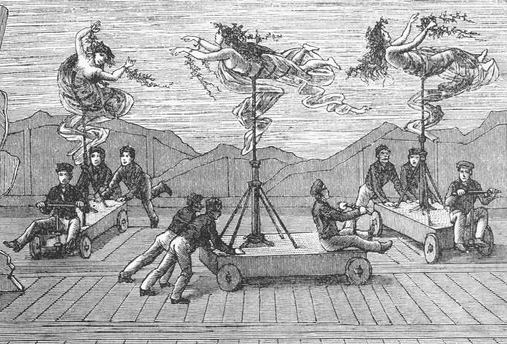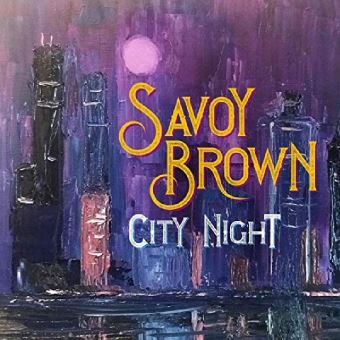以下、ブライアン・イーノさんによる、1976年のエッセイを訳出します。そのタイトルは、「芸術における多様性の創出と組織化(Generating and Organizing Variety in the Arts)」(☆)。
そして、《オブスキュア宣言》というそのまたのタイトルは、内容から判断して、私が命名しました。
以前に訳出した同イーノさんの《アンビエント宣言》(1978)と、ある意味で対になるテクストだろうか、これは──という気が、しましたもので(★)。
つまり……。少し、前せつを述べますと……。
ご存じのようにイーノさんは、ロキシーミュージックを1973年に解雇されてから、ソロのロック系ミュージシャンとして活動するかたわら、現代音楽のレーベル《Obscure, オブスキュア》を創始し運営しました(☆)。
そして1975〜78年の間に、オブスキュアは10作のアルバムを世に送りだしました(☆)。
ですが、入れ替わりに1978年からイーノさんは、《アンビエント》というコンセプトを提唱。以後は、その創始者であり絶対的な第一人者として、現在まで君臨しつづけています(☆)。
ちょうどオブスキュアのラスト・アルバムが、ハロルド・バッドさんによる『パヴィリオン・オブ・ドリームス』でした。オブスキュアからの作品で、もっともアンビエント的に聞こえるそれが、ターニングポイントを示す標石となりました。
そしてそのバッドさんが、アンビエントへと進んだイーノさんの盟友でありつづけたことも、おそらく皆さんはご存じでしょう(☆)。
という話のついでのようで心苦しいのですが、2020年12月に逝去されたバッドさん、その眠りの安らかなることを祈ります。
……そして。この〈オブスキュア→アンビエント〉への移行にさいしては、多少ならざる方針の変更が、ともなったものとも考えられます。
そして。《アンビエント》というコンセプトについて語っているのが《アンビエント宣言》だとして、それに先だったオブスキュア・シリーズのコンセプトの一端を語っているのが、以下のエッセイだろうか──、という気が私はしたのです。
では、本文のあとで、もう少し説明や補足を。──と思いましたが、しかしさいしょにいま、ひとつだけご説明!
ここでイーノさんは、次のようなものらを提示している感じです。
〈トップダウン方式の軍隊的システムによるクラシック音楽〉でもなく、〈アナーキーに帰するだけの“不確定性”を弄する前衛音楽やフリージャズ〉でもない──、〈ボトムアップ方式で自律的かつ有機的に調和し、かつ高度な訓練を受けた演奏家らを必要とせず、そして始まりも終わりもないような音楽〉、およびそれを現実のサウンドとする《システム》ら、を。
……と、いうことを頭に置いておくと、以下の文章の、和訳の稚拙さ、デテールの煩雑さ、そしてかなりの長さに悩まされることが、やや少なくなりそうな気がします!
いや打ち明けますと文章の前半、カーデューの楽曲のシステムについての語りが、すごく長いのです。が、そこらはななめ読みでもよさそうな感じ……ようは、ふしぎとうまく自律的に調和するのだと、《理解》してしまいましょう。では──。
《芸術における多様性の創出と組織化》
ブライアン・イーノ
楽譜とは、組織についての記述であり、音を出すための行動を組織するための装置のセットである。この観察が古典的な作曲ではそれほど明白ではなかったということは、組織が作曲上の重要な関心事ではなかったことを示している。
それどころか、組織単位(それがオーケストラであれ弦楽四重奏であれ、あるいは人間とピアノの関係であれ)は2世紀にわたって固定されたままで、作曲家の関心は、特定の指示を与えることで特定の結果を生み出すためにこれらの単位を使用することに向けられていたのである。
この後の実験音楽の考察に意味を持たせるために、クラシックの組織のパラダイムであるオーケストラの様相と意味を、詳しく説明したいと思う。
伝統的なオーケストラは、同時代に存在した軍隊と同じように、ランク付けされたピラミッド型の階層である。オーケストラのリーダーである指揮者、セクションのチーフ、サブチーフ、そしてさいごに一般メンバー、というのがランクの序列である。時には、ソリストがこのシステムの上層部に加わることもある。
もちろん、意図や願望を持った作曲家が、一時的ではあるものの、全体の構造やその行動を絶対的にコントロールしていることが暗示されている。このランキングは、軍事的なものと同様に、責任の度合いの違いを反映しており、逆に、行動に対する制約の度合いの違いを反映している。
ランク付けにはもう一つの効果がある。絵画における遠近法のように、〈焦点〉と〈視点〉を作り出すのだ。聴き手は、音楽には前景と後景があるような印象を受け、〈責任の重い〉出来事の多くは前景で起こり、後景はふんいきや対位法であることに気づかないはずがない。つまり、リスナーが利用できる知覚的ポジションの数は限られている可能性が高いということだ。
オーケストラのランキングシステムについて、3つめの見解を述べる。それは、訓練された音楽家の使用を前提としていることだ。訓練された音楽家とは、最低限、特定の指示があれば予測可能な音を出すことができる者だ。実際には、彼自身の自然な多様性の一部を抑制して、彼の信頼性(予測可能性)を高めるように訓練されている。
このエッセイでは〈バラエティ(多様性)〉という言葉を頻繁に使うことになるが、ここではその定義を試みたい。これは、サイバネティクス(組織の科学)からの用語で、W.R.アシュビー(W. Ross Ashby)が提唱したものだ。
システムの多様性とは、そのアウトプットの全範囲、その行動の全範囲のことである。有機的なシステムはすべて確率的であり、多様性を示し、生物の柔軟性(適応性)は、生成できる多様性の大きさの関数である。進化的な適応は、この確率的なプロセスと環境の要求との相互作用の結果である。
進化は、さまざまな出力を生み出すことで、可能性のあるさまざまな未来に対処する。この場合の環境とは、特定の系統を生存・繁殖させることで〈選択〉し、それ以外の系統を排除することで、多様性を減少させるものである。
しかし、生物が(その物質的性質によって)多様性を生み出すこと、また(その生存のために)多様性を生み出さなければならないことが明らかであるのと同様に、その多様性が無限であってはならないこともまた事実である。
つまり、進化を成功させるためには、アイデンティティの伝達だけでなく、突然変異の伝達も必要なのだ。逆に言えば、進化情報の伝達において重要なのは、正しいことだけでなく、少しでも間違っていること、有用な逸脱や突然変異が奨励され強化されることなのだ。
私の主張は、実験音楽の主な焦点は、独自の組織と、多様性を生み出して制御し、環境の〈干渉値〉である〈自然の多様性〉を吸収する独自の能力に向けられてきた、ということなのだ。
実験音楽は、クラシック(または前衛)音楽とは異なり、通常、ひじょうに具体的な結果に向けた指示を提供しないため、通常、完全に再現可能なサウンドの構成を指定しない。この種の音楽に、(私が思うに)誤解を招くような説明“不確定性”が言われる理由は、作品の正確な性質に対する関心の欠如である。
実験的作曲は、ユニークな(つまり、必ずしも再現可能である必要はない)出力を生成するシステムまたは組織を動かすことを目的としているが、同時に、これらの出力の範囲を制限しようとしていることを示したい。
これは、特定の目標ではなく、〈目標のクラス〉への傾向であり、1960年代に流行した〈目標のない行動〉(不確定性)という考え方とは異なるものだ。
このような方向性の変化を象徴するような、ある実験音楽をじっくりと扱ってみたい。
この曲は、コーネリアス・カーデューの『大いなる学び(The Great Learning)』からの「第7段落(Paragraph 7)」で、組織的なテクニックの大要であるだけでなく、レコードで入手できるという理由で選ばれた[...]。レコードに収録されているバージョンは、音楽家と美大生の混合グループによって演奏されており、私の経験は、私が参加した4回の演奏にもとづいている。
カーデューの楽譜はひじょうにシンプルである。あらゆるグループの演奏者のために書かれている(訓練された歌手を必要としない)。
孔子による文章があり、それは1語から3語の長さの24の短いフレーズに分かれている。各フレーズの横には数字が書かれていて、それはその行の繰り返し回数を指定している。そして、その行を何回大声で歌うべきかを示す別の数字もある。歌い方はほとんどが、ソフトだ(☆)。
歌い手は全員、まったく同じ指示を受ける。テキストの各行を指定された回数だけ、1回の息の長さで、1つの音で歌うことが求められる。合図で一斉にスタートし、各歌手は最初の行の音をランダムに選び、その行の繰り返しが終わるまでその音で歌い続ける。
そして、歌手は新しい音を選びながら次の行に進む。この音符の選択が重要だ。楽譜には次のように書かれている。〈仲間が歌っているのが聞こえる音を選びなさい。もし、音がなかったり、さっきまで歌っていた音しかなかったり、歌えない音しかなかったりした場合は、次の行の音を自由に選んでください。同じ音を2行連続で歌わないでください。それぞれの歌手は自分のスピードでテキストを進めていきます〉
楽譜をざっと見ただけでは、演奏によって曲が大きく変わってしまうような印象を受けるだろう。なぜならば、楽譜には各演奏者の行動の性質に関する正確な(つまり定量的な)制約がほとんど書かれていないし、能力の異なる演奏者自身が、訓練された音楽家集団のような意味での〈信頼性〉を持っていないからだ。
〔しかし、〕そのようなことが起こらないという事実は、スコアには規定されていない一連のコントロールが演奏中に生じ、この〈自動的な〉コントロールが作品の性質を決定する真の要因であることを示唆しているので、ひじょうに興味深い。
この命題が幻想ではないことを示すために、私はここで、楽譜に書かれた指示“だけ”が、結果に影響を与えるとしたら、この曲がどのように展開するかを説明する。そうすることで、この仮説的な演奏と実際の演奏との間の違いを明らかにし、その違いが〈自動〉コントロールの性質を知る手がかりになることを期待して。
仮説的な演奏。この曲は、豊かな持続性のある不協和音で始まる(〈最初の音には任意の音を選んでください〉)。歌手が次の行と次の音に移るポイントは、個々の息の長さによって決まるので(〈各行を息の長さ分だけ歌う〉)、異なるタイミングで音を変える可能性がある。彼らの音符の選択は3つの指示に影響される。それは、〈2行連続で同じ音を歌ってはいけない〉、〈聞こえる音を歌う〉、そして、何らかの理由でこれらの指示が守られない場合には、〈次の音を自由に選ぶ〉という3つの指示である。
ここで、20人の歌手がいて、たまたま全員が違う最初の音を選んだとする。その中の一人が、他の歌手よりも早く最初のラインの終わりに到達したとする。彼は自分の前の音を繰り返すことができないので、〈次の音〉として選ぶことができる音の数は最大で19個になる。彼は1つの音を選択し、利用可能な音の〈ストック〉を19個に減らす。次に交代した歌手は、18音の中から選ぶことになる。
この手順を続けていくと、曲中のさまざまな音が徐々に減っていき、3つの音程指示のうち3つめの音程指示に従って新しい音を恣意的に導入しなければ曲を続けられないほど、利用できる音が少なくなることが予想される。歌手の数が多ければ、この減少のプロセスは曲全体に及ぶかも知れない。
つまり、この仮説的な演奏では、曲の全体的な形は、大量のランダムな音符のストックが、小さく、均一で、時々補充される、同じようにランダムな音符のストックへと減少していく(これらは、最初のストックの残りか、ランダムに追加されたものだからである)。
実際の演奏。この曲は、同じように豊かな和音で始まり、急速に(つまり、最初の行の終わりに到達する前に)、複雑だが目立った不協和音ではない和音へと変化していく。その後すぐに、仮説的な演奏よりもはるかに高いレベルで、多かれ少なかれドローン音を中心とした和音で回転する傾向のある、特定のレベルの多様性に〈落ち着く〉のだ。
このレベルの多様性は、曲の残りの部分でかなり密接に維持される。演奏者が〈次の音を自由に選んでください〉という指示に頼らなければならないことは稀であり、少数の歌手の場合を除いて、この指示は冗長であるように見える。
なぜなら、演奏者が意図しなくても、常に新しい音が曲の中に入ってくるからだ。これは、演奏者の意図とは関係なく、常に新しい音が曲に導入されているからである。
そして、この観察は、曲中の音符のストックを補充するために働く一連の〈事故〉の存在を指摘している。まず第一に、混声合唱団の〈頼りなさ〉が挙げられる。きょくたんな話、音痴のシンガーがある音を聞いて、〈聞こえる音を歌え〉という音程の第一指示に従って、その音と新しい音を〈合わせる〉ことは十分に可能だ。また、無意識のうちに歌いやすいオクターブに移調したり、和声的に近い音(3度や5度)を歌ったりする歌手もいるだろう。
純粋に外部の物理的な出来事も、新しい音を導入する傾向がある……ビート周波数の現象だ。ビート周波数とは、音程の近い2つの音を鳴らしたときにできる新しい音のこと。これは数学的に関係しており、和声的には関係していない。以上、新しい素材が導入される方法を3つご紹介した。
楽譜に書かれている〈バラエティを減らす〉条項(〈聞こえる音を歌う〉、〈2つの連続したラインで同じ音を歌わない〉)以外にも、演奏時に発生するものがある。そのひとつは、演奏する部屋の音響特性に関係するものだ。
大きな部屋であれば(この曲のような規模の演奏が可能な部屋はたいてい大きい)、共振周波数があると考えられる。これは〈筐体が共鳴する音程〉と定義されているが、実際には、〈ある振幅で鳴らした音が、その音の周波数と同じ共振周波数を持つ部屋では、同じ振幅で鳴らした他の音よりも大きく聞こえる〉ということを意味する。
つまり、複数の音が均等な振幅で鳴らされている場合、部屋の共振周波数に対応する音は、他のどの音よりも大きく聞こえるということ。「第7段落」では、この事実により、環境的に決められた音を中心に曲が流れていくという統計的な確率が生まれる。それが、先ほどほのめかしたドローンの音かも知れない。
バラエティを減らす、もう1つの重要な要素は、好み(テイスト)である。演奏者は多くの場合、かなり広い範囲の音を選択する立場にあるが、どの〈系統〉を強化するか(暗にどの〈系統〉を除外するか)については、それぞれの文化的歴史や嗜好が重要な要素となる。
これにはもう一つの側面がある。音痴でない限り(あるいは訓練を受けた歌手でない限り)、周囲とひじょうに不調和な音を維持することはひじょうに困難だ。一般的には、ほとんど無意識のうちに音を調整して、周囲と何らかの調和的な関係を形成する。これが、最初の不協和音が急速に細くなる理由である。
要約すると、この曲における音符の生成、分配、制御は、次のように支配されている。
1つの特定の指示(〈2つの連続した行で同じ音を歌ってはいけない〉)、1つの一般的な指示(〈聞こえる音なら何でも歌う〉)、2つの生理学的要素(音痴と移調)、2つの物理的要素(ビート周波数と共鳴周波数)、そして〈好み〉という文化的要素である。
もちろん、曲の他のパラメータ(特に振幅)も同様に制御され、同様の分析技術に従うものだし、曲の〈呼吸〉の側面は、曲の最も重要な特徴である瞑想的な静けさや落ち着きを生み出すかも知れない。
しかし、ここまで述べてきたことは、古典的な作曲技法とは全く異なることが行われていることを示すのに十分だろう。つまり、作曲家は、演奏の際に生じる多様性を無視したり抑制したりするのではなく、その多様性こそが音楽の本質であるように作品を構成しているのだ。
おそらく、多くの実験音楽を特徴づけるこの種の作曲の最も簡潔な説明は、サイバネティクス研究者のスタッフォード・ビア(Stafford Beer)による声明で提供されている。彼は、次のように書いている。〈完全に詳細に指定しようとするのではなく、ある程度だけ指定する。そうすれば、システムのダイナミクスに乗って、自分の行きたい方向に進むことができる〉。
カーデューの曲の場合、〈システムのダイナミクス〉とは、演奏を取り巻く環境、生理的、文化的な環境との相互作用である。イギリスの作曲家マイケル・パーソンズ(Michael Parsons)は、このような作曲について別の見方をしている。
一つの活動を複数の人が同時に行うことで、皆が少しずつ違うやり方をするという考え方で、〈単一性〉が〈多元性〉になることで、ひじょうに経済的な表記方法が可能になる。一つの手順を指定するだけでよく、みんなが違うやり方をすることで多様性が生まれる。
これは、民族音楽ではともかく、クラシックのコンサート音楽では全く無視されている、(才能や能力ではなく)自然な個人の違いという意味での〈隠れた資源〉を利用した例である。
自然な変化を作曲の手段とする動きは、マイケル・ナイマン(Michael Nyman)の「1-100」という作品に例示されている。
この作品では、4人のピアニストがそれぞれ100個の和音を鍵盤の下にゆっくりと降りてくるように演奏する。最後の和音が聞こえなくなったら次の和音に移るように指示されている。
この判断は、様々な変数(コードを弾いた音の大きさ、奏者の耳の良さ、ピアノの状態、コードが聞こえなくなったと判断した時点)に左右されるため、4人の奏者は急速に息が合わなくなっていく。その後には、最大4つの異なる和音によるユニークで繊細なクラスターが形成されたり、急速な和音の連なりの後に長い沈黙が訪れたりするのである。
これは、パーソンズが指定した作曲技法をエレガントに使用したもので、カーデューの作品と同様に、現在ではあまり重要視されていない要素である聴き心地のよさがひじょうにきわだっている。
この種の作曲は、作曲上の変化と同様に、聴き手の知覚上の変化をもたらす傾向がある。興味深いのは、この2つの曲の録音では、曲の終わりが〈フェード〉になっていることだ(カーデューの楽曲は、始まりもフェードイン)。
これは、曲が終わったということではなく、耳に届かないところで曲が続いていることを意味している。フェードアウトの構成的価値を真に利用しているのはロック音楽だけであり、それらの作品はレコードの片面には長すぎるという意味で、便宜的に使われている。
しかし、フェードアウトは、この作品の一般的な質とひじょうによく調和しており、他の実験音楽と共通する重要な特徴を示している。それは、音楽が仮想的な連続体の一部分であり、特に方向性を持たないということだ。
この仮定の妥当性を検証するために、ベートーヴェンの交響曲第9番の途中でフェードアウトしているところを想像していただきたい。クラシック音楽のエネルギーの多くは、主題と変奏という一つの曲想から別の曲想への移動から生まれる。この移動は、曲の歴史と将来の可能性が、現在聴いている曲の認識に関係しているという意味で、方向性を持っている。
しかし、実験音楽では、限られた数の要素をある瞬間に同時に変化させたり、いくつかの時点の関係性に関心を持つようになった。また、作曲のアイデアを練る時間のスパンを短くする傾向がある。
その結果、ギャヴィン・ブライアーズ(Gavin Bryars)の「イエスの血は決して私を見捨てたことはない(Jesus' Blood Never Failed Me Yet)」のような、周期的な形式が使われるようになった(興味深いのは、この作品も「第7段落」も「1-100」も、すべて〈見出された素材〉をもとにしていて、その素材を再構成することに作曲家の関心が向けられていることだ。この状況では、特別な作曲上の自由がある)。
私は、芸術の歴史が、あるアイデアが別のアイデアを打ち負かすような、劇的な革命の連続であるという見解を支持するつもりはない。私は、古典的な作曲技法と実験的な作曲技法、そしてそれぞれがリスナーに促す知覚様式をいくつか区別したが、一方から他方への発展が単純な上昇過程であると提案したいわけではない。
私はこの2つの音楽が互いに排他的であるかのような特徴を与えてしまったが、事実上、どのような例をとってみても、どの作品にもそれぞれの方向性の側面が存在することが分かる。私が主張しているのは、音楽の発展とは、新しいハイブリッドを生み出すプロセスであるということだ。
たとえば、右手に〈演奏の多様性を抑制する傾向がある〉、左手に〈演奏の多様性を促進する傾向がある〉というラベルを貼った〈志向性の尺度〉を提案することができる。
このスケールの両極を占める作品を見つけることはひじょうに困難だが、スケールに沿ったポイントで明確な作品を見つけることは難しくない。古典的なソナタは、記譜法の欠点だけが原因である場合でも、演奏にある程度の多様性をもたらす。
一方、左側の、最もランダムなランダム音楽(その言葉が何を意味するかはともあれ)は、物理学の単純な法則に至るまで、あらゆる要因によってその範囲が制限されている。であるから、カーデューの曲は左に位置するかも知れないが、フリージャズの即興演奏のように左に位置することはないだろう。この種のスケールは、そこに配置される音楽について多くを語るものではないが、その機能は、不連続性ではなくハイブリッドの観点から考えることを思い出させてくれる。
以上のように、音楽の考え方を対立させることには抵抗があるが、ここでは2つの組織構造について述べたいと思う。私が言いたいのは、クラシック音楽が一方で、現代音楽が他方であるということではなく、それぞれが2つの構造のいずれかに傾いたハイブリッドのグループであるということだ。
極端な例として、こういうタイプの組織がある。それは、受動的(静的)であると想定される環境の中で、既に定義・特定された解決策に向かって、厳格にランク付けされたスキル指向の構造である。このタイプの組織は、環境(およびその多様性)を一連の緊急事態とみなし、この多様性を中和または無視しようとする。観察者は、(ランキングシステムの知識と、組織の様々な部分に与えられた自由度の違いの両方によって)ランクの上層部に注意を向けるように促される。彼は、価値のヒエラルキーを印象として与えられる。
この組織は、よく機能する機械のようなふんいきを持っている。ある種のタスクに対しては正確かつ予測可能に動作するが、適応性はない。自己安定性がなく、変化や新しい環境条件を容易に吸収することができない。さらに、動作させるためには特定のタイプの命令を必要とする。
サイバネティクスでは、このような命令をアルゴリズムと呼んでいる。スタッフォード・ビアの定義では、〈既知の目標に到達するための包括的な指示〉とされており、〈信号を左折して20ヤード歩く〉という指示もアルゴリズムだし、〈C#を8分音符、Eを16分音符で演奏する〉という指示もアルゴリズムである。このような具体的な戦略は、フォルム(またはアイデンティティ、またはゴール、または方向)の正確な概念がすでに存在し、その概念が静的で単一であることが当然である場合にのみ考案できることは明らかだろう。
上述の組織構造とは逆の組織構造を提案しても、それに組織という名前をつけることはないだろうから、意味がない。なぜならば、その言葉が意味するものが何であれ、それには何らかの制約のアイデアと、アイデンティティのアイデアが含まれていなければならないからだ。
そこで、これから説明するのは、ある種の有機的なシステムを代表する組織のタイプであり、その最も重要な特徴は、〈環境の変化には適応性のある生物が必要である〉、という事実にもとづいている。
さて、生物とその環境との関係は高度で複雑なものであり、ここではそれを扱うことはできない。しかし、適応性のある生物とは、周囲の環境の変化に対応して自らの行動を監視(調整)するメカニズムが組み込まれている生物であると言えよう。
この種の生物は、周囲の現実の座標が複雑すぎて特定できないか、予測不可能なほど変化しているため、特定の戦略(または特定の未来のための特定の計画)が役に立たないなら、別のタイプの指示で動作することができなければならない。
ここで必要となる指示はヒューリスティック(発見的手法)と呼ばれ、〈未知のゴールを探索するための指示であり、ある既知の基準に従って継続的または反復的に進捗を評価するもの〉と、定義されている。
ビアの例で言えば、霧に包まれた山の頂上に到達する方法を教えたい場合、〈上に向かって進みなさい〉というヒューリスティックな方法で到達することができる。このようにして活動する生物は、中央集権的な制御構造だけではない。そして、環境の不規則性を、自らのアイデンティティを形成し、調整するための一連の機会と考えなければならない。
私がこのエッセイで提案しようとしたのは、現代音楽をその機能の観点から議論するための手法である。私が主に一つの音楽に集中したのは、この手法が一つの特定の問題に有効であることを示したかったからであり、また、この手法はその後、他の活動を扱うために極めて容易に一般化できると感じたからである。
このアプローチの範囲を音楽に限定したいわけではないが、音楽は社会芸術であり、それゆえに何らかの明示的な組織的情報を生成するので、このような分析には容易に適している。
私はこれまで、芸術だけでなく、例えば、現代スポーツの進化や、伝統的な軍事戦術から現代的な軍事戦術への移行などについても、活動の組織レベルに向けて同じような質問をして議論してきた。このように、一見すると異なる進化を遂げてきたものが、システムレベルではひじょうに正確な類似性を持っていることは驚きではない。
モース・ペッカム(Morse Peckham)の著書『カオスに対する人間の怒り』には、〈芸術とは、人間が現実の世界の緊張や問題にさらされることに耐えるために、偽りの世界の緊張や問題にさらされることである〉と書かれている。
環境の多様性が時間と空間の両方で拡大し、世界の運営を説明すると考えられていた構造が次第に機能しなくなるにつれて、また別の組織の概念が、最新のものにならなければならない。これらの概念は、停滞ではなく変化の仮定と、確実性ではなく確率の仮定にもとづいている。現代アートは、そのような感覚を私たちに与えてくれているのではないだろうか。
──と、いうことです。
では、本文のあとの説明や補足をいくつか。まず、原文とその訳し方について。
テクストは、ネット上のPDFを原文としています。これの存在をツイッターで広報してくださった、アカシ6ix9ineさんに大きな感謝です(☆)。
そしてそのPDFが、印刷物のスキャンでありながら、何か〈OCR〉的なことでテクストデータを含んでいるのですが──ありがたいと思うけど仕組みは知りません──、しかし、読み取りのバグだらけです。それらを、目視&手動で修正しました。
そうして校訂されたような英文テクストを、DeepLおよびGoogleの、自動翻訳システムに通しました。両者の出力が一長一短なので、双方のよさそうなところをつぎはぎ。
しかしそれでもバグだらけなので、目視&手動で訳文を修正しました。かつ、語調や訳語らをなるべく統一しました。
また私の独断で、少しでも読みやすくなるよう、改行を大量に追加しています。原文の本来のパラグラフの切れめは、行間の開きが示しています。
あと。すみませんけれど、注釈のところは省略しました。
というか本文についてさえ、〈ぜひ刈り込みたいっ、中略で短くしたい!〉という衝動に襲われつづけましたが。しかし相手が他ならぬイーノさんなので、そこまでの不遜はできません。
訳語について。この原文は、まずイーノさんたちの立場を〈実験音楽, Experimental music〉と呼びながら、始まっています。それと対比されるのが〈クラシック音楽, classical music〉、および〈前衛音楽, avant-garde music〉です。
ところが文章のさいごのほうは、〈実験〉ではない〈現代音楽, contemporary music〉を、イーノさんたちが背負うかたちになっています。これはもともとです。
次に、補足です。
ここでイーノさんが利用している、《サイバネティクス》の概念について。
それは本来、生体のそなえている〈恒常性〉を保つシステム──負のフィードバックなど──を、工学に応用しようくらいなアイデアでしょう。もちろんイーノさんは、それを正しく理解しています。
けれども現在は、デジタルっぽい事物らについて、派生した〈サイバー〉という形容詞が使われます。それは一種の誤用なので──本来のサイバネはアナログ的でオーガニックなものです──、まあ通用してしまっているものは仕方ないですが。
しかし、それではないということです。離散的(デジタル)に精細ではない、大まか(アナログ)な指示こそがうまく機能する、という文中のお話からもお分かりのように。
そしてさいご、私の感想や考察のようなことを。
ナイマンさんの「1-100」についていわく、〈現在ではあまり重要視されていない要素である聴き心地のよさがひじょうにきわだっている〉。ほんとうにいいですよね!
もちろんイーノさんの立場はそれなので、耳に愉しくない音楽に関わったことは一貫して、ほぼありません。そこが、レベルの低い自称の前衛や実験主義者らとは、まったく異なるのです。
しかし、まあ。文中にも出ている《ポーツマス・シンフォニア》の、あまりにも下手くそすぎる“名曲迷演”……。あれあたりは、ちょっとあれでしたが!
また、〈フェードイン/フェードアウト〉の効果を積極的にとらえること。その効果が、〈始まりも終わりもない〉という感覚およびコンセプトを、増強します。
そういえば、まさにこの時期のイーノさんの名作『ディスクリート・ミュージック』、そのA面の曲について……。
それを初めて聞いた子どものころ、〈いくらなんでもフェードインがスローすぎるっ!〉と、もどかしさを感じたことを想い出しました。実は、いまでも少しは思います!
そして、ほんとうのさいごに。
“すべて”にすぐれたイーノさんですが、その最大の長所であり学ぶべき点は、《システム志向》というところです。たんに“いい曲を作る”のではなく、いい曲らを生みだすためのシステムの創造や構築に、つねに留意すること。
そういうお方を元祖としているのですから、本来は《アンビエント・ミュージック》と称しているもの全体が、システムを志向しているべきと考えます。
とはいえ、聞いたらすぐ視えてしまうようなシステムは、造りが浅いわけなので。ですからそこらがつかめなくても、聞いた感じがよければいい、と割りきっていますけれど!
そして──。この1976年におけるイーノさんは、練度の高くない演奏者たちのオーガニックな協調と、会場そのもののアンビエンスが導くような、そういうシステムを称揚していたわけです。
ところが。イーノさん本人の創造によるシステムや楽曲らは、そんなにはオーガニックな感じがしない。どちらかといえばメカっぽく、もしくはテクノっぽい、という印象がもっぱらではないでしょうか。とくに、《アンビエント》以降について。
これはそういうイーノさんの個性であり、文中で言われた〈好み〉によることなのでしょうか。メカが好き、そして独りであることが好き、というような……。私には共感しかありません。